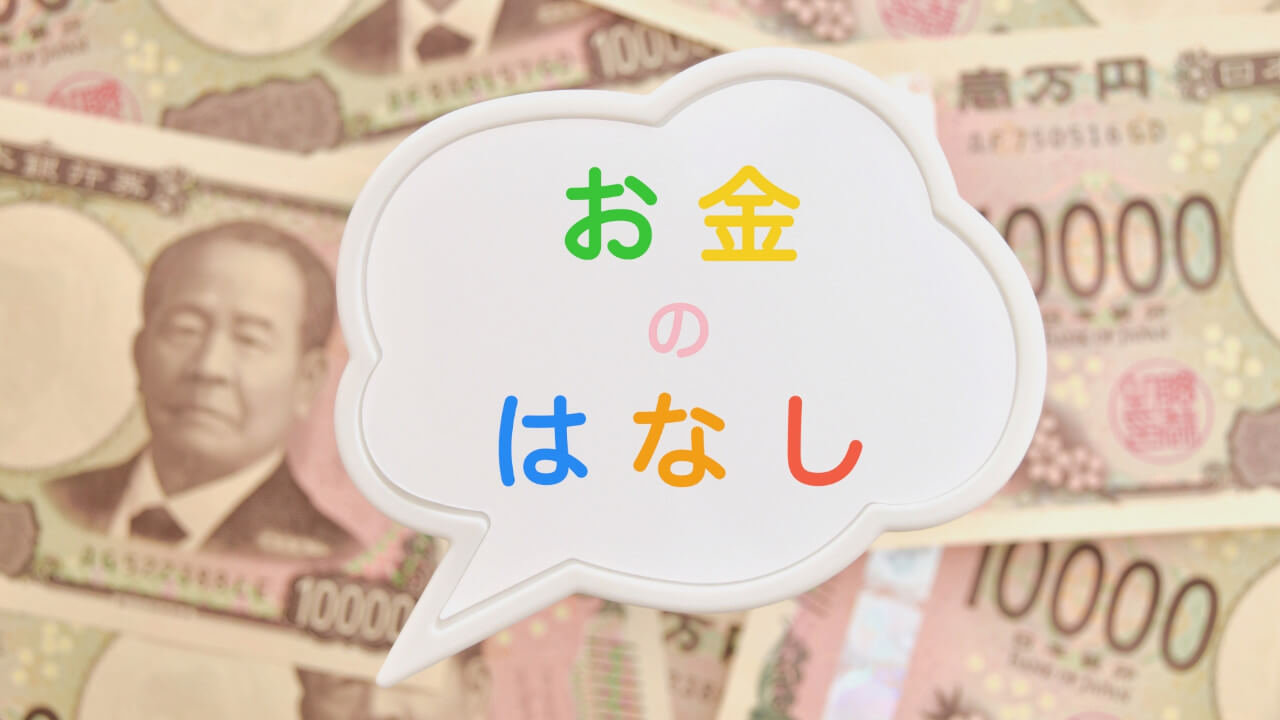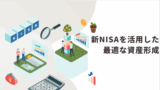お金の話は恥ずかしい?
「お金の話をするなんて、なんだかはしたない気がする…」
日本では、そんな空気がいまだに根強く残っていますよね。

お金に執着するのは恥ずかしい
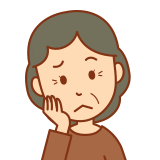
収入や資産の話をすると、いやらしいと思われそう
そんな感覚に心当たりがある方も多いのではないかと思います。
でも、それって本当に正しい感覚なのでしょうか?

少なくとも、お金を避けている人がお金持ちになれることは無いでしょう。
なぜ日本では「お金の話=下品」とされてきたのか?
ネットで調べてみたところ、こうした価値観は、実は歴史的な背景に根ざしているようです。
江戸時代には、武士階級が「金銭に執着しないこと」を美徳とし、商人や金儲けを卑しいものと見下す風潮がありました。
さらに戦後の教育では「お金は努力の対価として自然に得られるものであり、積極的に語るものではない」という考え方が根付いていきました。
こうして、「お金の話は下品」「お金に興味を持つのははしたない」といった価値観が長く社会に残ってきたようです。
しかし、今の時代にはそのまま通用しない場面が増えています。
お金の話を避けることの“損失”
お金の話を避けることで、次のような機会を逃してしまいがちです。
投資を「危険」と思い込み、学ばない
正しい知識がないと、「投資=ギャンブル」「借金まみれになる」といった誤解を持ったままになり、資産形成のチャンスを失います。
情報交換の場がなくなり、損をしやすくなる
「保険どうしてる?」「住宅ローンの金利って?」といった話を避けていると、知恵や工夫をシェアしあう機会がなくなり、結果として不利な選択をしがちです。
でも、何でも話せばいいわけではありません。
ここで注意しておきたいのが、「お金の話をすること=何でも話していい」というわけではないということです。
SNSや職場、ちょっとした会話で「〇〇万円投資してる」「資産が〇〇ある」といった話をすると、思わぬところで詐欺の標的になったり、妬みやトラブルの原因になることもあります。
- 「NISAってこんな制度らしいよ」
- 「こんな本を読んでお金のことがわかってきた」
- 「うちでは家計簿アプリを使ってこんなふうに支出を見直してる」
こういった話なら、プライバシーを守りつつ、健全に金融リテラシーを高め合うことができると思います。
次の世代にも“お金は触れてはいけない話”という意識が引き継がれる
子どもに「お金の話はしちゃいけません」と教えることで、お金の知識がないまま大人になってしまう悪循環が続きます。

アメリカや富裕層の家庭では、子どもに対する金融教育は積極的に行われており、学校教育にも取り入れられつつあります。
日本でも「お金は学ぶもの」という文化が根付くと良いなと思います。
今こそ「学び」と「対話」を
ここ十数年間を見てみても、時代は変わったと思います。
今の日本には、国が整備した資産形成の制度も数多く存在します。
- NISA(少額からの長期投資支援)
- iDeCo(老後資金の積立を非課税で支援)
- インデックス投資やETFといった分散投資の普及
こうした制度を正しく理解し活用するには、お金に対する「偏見」ではなく「知識」が必要です。
お金を語れる人が、自由な選択を手に入れる
お金の話を前向きに学び、語れるようになると──
- お金への不安が減り、人生設計に余裕が生まれる
- 投資や節約で資産を築く力がつく
- 働き方・暮らし方に多様な選択肢が持てる
お金について考え、話すことは、自分の人生を守り、豊かにするための「知的な行動」です。
まとめ
お金の話を避けることが、最大のリスクになる時代へと変わりました。
「お金の話はタブー」という思い込みを手放し、知識と冷静な判断力を武器に、賢く資産形成していきましょう。

FIREを目指す人だけでなく、すべての人が金融リテラシーを身につければ、よりよい未来が実現できると考えています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
お金の話をするときに気を付けることを別の記事に書きました。併せて読んでみてください。