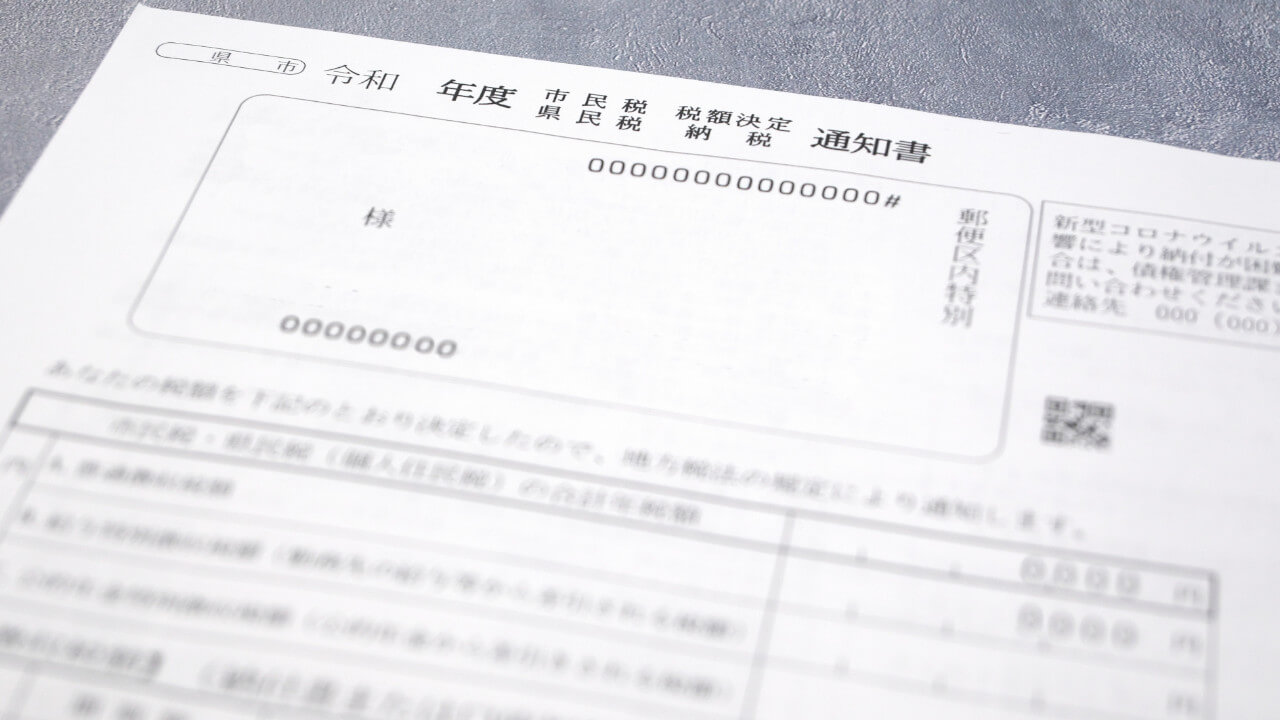住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、会社を辞めた後も支払いが残ることがあります。
会社員の時は、住民税は特別徴収により給与から天引きされていましたが、退職後は普通徴収に切り替わるのが一般的です。
普通徴収の場合、居住している自治体から納税通知書が郵送されてきますので、自身で納付する必要があります。
住民税の4つの納付方法
納税通知書と併せて4つの納付方法を紹介する案内書が入っていました。
- ATM
- コンビニ・窓口
- 自宅
- 口座振替
一つずつ検討していきます。
ATMで納付

案内書には窓口で待たずにOK!とメリットが記載されていました。
スマホやネットバンキングが使えない人にとっては、これが一番良い方法に思いますが、そうでない人は別の方法が良いでしょう。
コンビニ・窓口で納付

領収証書が必要な人はこれ一択です。ほかの方法では領収証書の発行ができないためです。
コンビニ等の店頭では、原則スマホアプリ、クレジットカード、電子マネーでの支払いができないため、納税額が大きい場合には向いていないと思います。
自宅で納付

スマホを持っている人やネットバンキングが使える人にとっては、これが一番良い方法に思います。
自宅で納付する方法は3つあります。
スマホ決済アプリ
PayPayなどのアプリから「請求書払い」を選択し、納付書のバーコードを読み取り、支払い手続きをするだけです。
決済手数料はかかりません。
クレジットカード
スマホまたはタブレットに『モバイルレジ』アプリをインストールし、納付書のバーコードを読み取り、支払い手続きをします。
但し、クレジットカード払いの場合、納付額に応じて決済手数料がかかるのが難点です。
ネットバンキング
ネットバンキングにログインし、「ペイジー」を選択して納付書に記載の情報を入力して、支払い手続きをします。
金融機関によって利用時間や時間外手数料などが異なるので注意が必要です。
口座振替で納付

案内書には納め忘れの心配なし!とメリットが記載されていました。
但し、口座振替の申し込みには、役所の窓口に行くか口座振替依頼書を記載して郵送しなければならないため時間と手間がかかります。
まとめ
前述の特徴やメリット・デメリットを踏まえると、それぞれの人に向いている納付方法は下記のようになるかと思います。
- 領収証書が必要な人 → コンビニ・窓口で納付
- スマホを持っている人 → スマホ決済アプリで納付
- ネットバンキングが使える人 → ネットバンキング(ペイジー)で納付
- それ以外の人 → ATM or 口座振替で納付
なお、クレジットカードでの納付は決済手数料がかかるので、積極的に利用する理由は無いかと思います。

私は普段からPayPayや楽天Payを利用しているので、スマホ決済アプリで納付する方法を利用しました。
また、これらの納付方法は住民税の他に、軽自動車税(種別割)や国民健康保険料などでも利用できます。
以上、参考になれば幸いです。